コンテンツ
- ホーム
- 保険毎日新聞コンテンツ
- 特集
- 特集
リスキリングで新たな高みへ~SOMPOチャレンジド
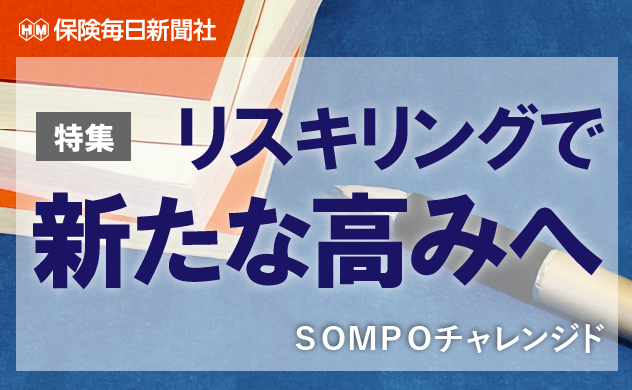
本特集では、リスキリング(職業能力の再開発、再教育)によって社内外に活躍の幅を広げている人物を紹介する。今回は、5人以上の障害のある従業員が働いている事業所で配置が義務付けられている「障害者職業生活相談員」の資格を取得し、損保ジャパンの障害者雇用始動期に障害者の業務指導に携わった他、現在は特例子会社のSOMPOチャレンジドに出向し、SOMPOグループ全体における障害者の活躍推進などに携わる浅野登紀子氏に話を聞いた。
SOMPOチャレンジド 浅野登紀子 氏
理想は「障害者雇用」の概念のない世界

グループ障害者活躍支援室教育定着支援グループ・グループリーダー
SOMPOの障害者活躍推進支える
きっかけは小学校の保護者向け勉強会
浅野氏は、今はSOMPOチャレンジドに出向する立場だが、1990年に損保ジャパン(旧安田火災)に入社してから営業推進部に長く所属していた。主に自動車関連の保険代理店を担当し、整備工場代理店の従業員がメカニックの知見を生かして地域の車いすの整備や清掃を行う活動など、地域と代理店をつなぐ社会貢献活動の旗振り役なども担ってきた。
そうして営業推進に取り組んできた折、自身の二人目の子どもに知的障害があることが判明する。その子を健常児と障害児とを同じ施設で教育する「インクルーシブ教育」を行う小学校に入学させたところ、その学校では積極的に障害者に関する保護者向け勉強会を実施しており、勉強会を通じて、障害者の働き方として企業就労と福祉就労があることや、障害者雇用の促進・安定のためにつくられた特例子会社の存在を知り、障害者雇用に興味を持つようになる。浅野氏は「時間の経過とともに障害者雇用への関心は高まり、SOMPOチャレンジドの設立計画を知ったときには、ぜひそこで働いてみたいと考えていた」と振り返る。
2018年のSOMPOチャレンジド設立後は、年に1回上司に提出する個人の中長期の目標、マイキャリアプランでSOMPOチャレンジドへの出向の希望を伝えていた。そんなある日、上司から3人の障害者を雇用するにあたり、その3人の指導役を担ってほしいと打診される。浅野氏は将来に向けてキャリアを積むよいチャンスだと捉え、その依頼を引き受けた。
浅野氏は、「配属された3人にはそれぞれ異なる障害があった。二人目の子どもが通う学校の勉強会で学んだ知識、会社から提供された資料などを活用しながら、それらの人たちはどのような特性があるのか、どのような配慮が必要なのかを伝えるため職場への勉強会を定期的に開催し、できる限り彼らをスムーズに受け入れてもらえるように努めた」と話す。
そうした立場で障害者の業務指導も手掛ける中、同氏は「障害者職業生活相談員」の資格を取得した。「障害者への理解はもちろん、障害者雇用制度そのものの理解ももっと深めなければと考え、人事に相談して取得させていただいた」という。同資格は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する、合計10時間以上(複数日に分けて実施)の「障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講すれば取得できる。
「障害者雇用」研修を積極的に実施
希望がかないSOMPOチャレンジドに出向した現在は、グループ障害者活躍支援室に所属し、SOMPOグループ全体における障害者雇用の他、障害者の活躍や定着を後押しする取り組みに携わる。昨年は同グループ各社の部門リーダーや障害者の指導担当者などに向けて、合計14回のオンライン研修(他、本社での対面研修2回)を企画・実施し、延べ1000人以上が参加した。これらの研修について、「例えば、発達障害のある人は音が苦手な方もいる。そうした人は音をある程度遮断するイヤーマフを装着することで業務に集中することができるが、障害特性に対する知識のない人からは『あの人は仕事中に音楽を聞いている』などと指摘される可能性があるため、そのような誤解を生まないために実施している」と話す。
同氏はこれまで、障害のある社員の中で健常者の社員と同等、むしろそれよりも高度な業務を遂行しているケースを数多く見てきたと述べる一方で、何不自由なく働いているように見える健常者の社員の中にも、育児や介護といった家庭内の問題、ケガや病気といった自身の問題を抱えている社員は当然たくさんいると話す。その上で、「『障害者雇用』という概念がなく、健常者と障害者が同じ職場に在籍し、お互いが配慮し合いながら働ける環境が理想だ。そこに少しでも近づけられるような活動を今後もしていきたい」と先を見据える。
昨今は障害者雇用以外にも女性活躍推進、テレワークの導入等による働き方改革など、保険会社各社でもDE&I(多様性、公平性、包摂性)の取り組みが浸透しているが、浅野氏は自身の経験から会社でDE&I関連で新たな制度を導入したときは、その制度の利用者が主体的に改善点などを発信するべきだと話す。
同氏は第一子を産み、産前産後休業や育児休業制度を利用した当時について、「産休や育休の制度ができて間もないころだったこともあり、私が不在中の仕事を代わりに行う人員が補充されないなど、会社の対応に不十分な点が多かった」と振り返る。職場の同僚が「代わりの人員を補充してほしい」と会社に訴えてもただ不満を言っているように受け取られる可能性が高いと考え、同僚への負担が増えないように配慮してほしいと育児休業制度からの復帰後には自ら会社に伝えたという。自身を含めた制度利用者と会社との対話の積み重ねにより、産休や育休などに関しては今の安定した内部体制が整備されたと思っているとし、これからも、より働きやすい環境づくりのために制度が導入された際には、その制度の利用者が積極的に改善点などを発言できる環境が整うとよいと述べている。



