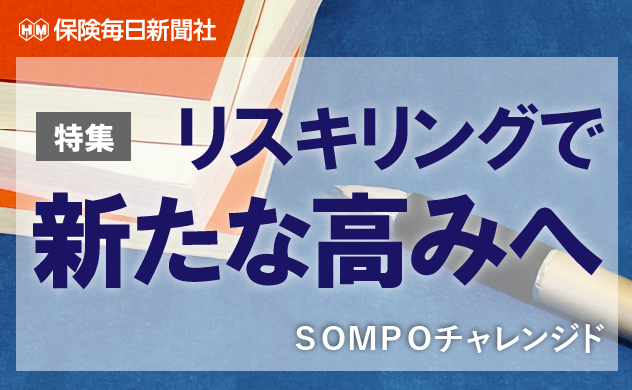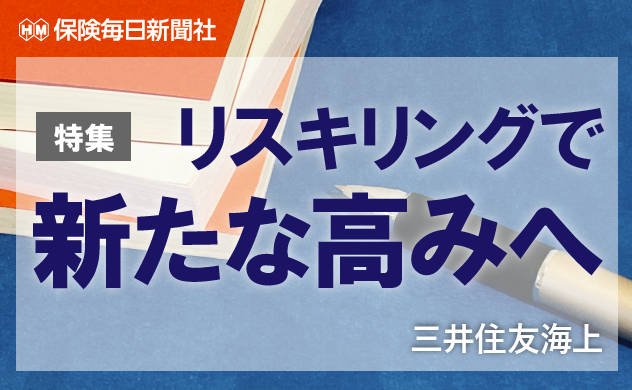コンテンツ
- ホーム
- 保険毎日新聞コンテンツ
- 特集
- 特集
リスキリングで新たな高みへ~日本生命
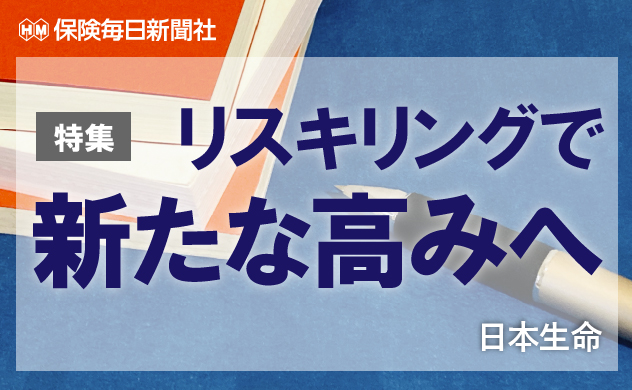
本特集では、リスキリング(職業能力の再開発、再教育)によって社内外に活躍の幅を広げている人物を紹介する。今回は、日本生命に入社してから20年以上のキャリアの中で社会保険労務士、産業カウンセラー、消費生活アドバイザーの三つの資格を取得し、社内の健康保険制度の管理・運営、職員の健康管理、メンタルヘルスケアなど、社内の福利厚生支援を中心とする業務に携わる大長智子(だいちょう・ともこ)氏に話を聞いた。
日本生命 大長智子 氏
社労士等取得し社内の福利厚生支える

総務部東京総務グループ担当課長
生き生きと働くための環境づくりをしていきたい
資格取得は担当業務や後のキャリア形成のため
大長氏は1999年に新卒で日本生命に入社し、大阪本店の総務部厚生グループに6年間所属した後、2005年に東京本社に移って健康管理室(現健康経営推進部)に11年在籍し、その後コンプライアンス統括部コンプライアンス推進グループ、法人営業企画部と合計四つの部署を経て、現在は総務部東京総務グループの担当課長を務める。
三つの資格についてはそれぞれ、社会保険労務士、産業カウンセラーは健康経営推進部所属時、消費生活アドバイザーはコンプライアンス統括部所属時に取得した。
大長氏が取得したこれらの資格は働きながら取得できるものだが、いずれも簡単ではない。それぞれの平均的な合格率は、社会保険労務士が約6~7%、産業カウンセラーが約60%、消費生活アドバイザーが約30%となっており、社会保険労務士については、同じ難関国家資格として人気の行政書士と司法書士の中間ほどの難易度と言われている。また、比較的合格率の高い産業カウンセラーについても、大学や大学院で指定の単位を取得していない場合は養成講座の受講(大長氏は7カ月コース(当時)を受講)が必須であり、一定の学習時間の確保が必要となる。また、消費生活アドバイザーについては、産業カウンセラーのような講座の受講などは必要なく誰でも受験可能だが、試験では消費者問題や経済に関する法律など幅広い分野の知識が求められ、一般的に合格に必要な学習時間の目安は約300時間と言われる。
大長氏はこれらの資格を取得した理由について、「実務経験に加え、より知識を深掘りすることで今後のキャリアとして希望する部門の業務に役立てたいと思った他、入社以降、自分自身に“これがある”と思える強みがないと感じており、所属した各部署でそうした気持ちの部分を補強する面でも資格の取得に励んだ」と話す。
社会保険労務士については、同社では独自の健康保険組合を有しており、同氏自身も総務部厚生グループ所属時、同社の健康保険制度の運営や管理、健康増進取り組みに携わる業務を担当していた。健康保険は社会保険の一分野であるため、健康保険法を含めた社会保険労務士の試験科目10科目全般の法律等について、より客観的で専門的な知識を身に付けたいと考えるようになったことが取得を目指すきっかけだという。
産業カウンセラーについては、産業医、看護師、保健師(カウンセリング業務担当)といった専門職に加え、事務職とさまざまな職種が協力して業務を進めるという健康経営推進部の特性が資格取得の動機につながっているという。取得当時、同氏は職員の健康管理業務に携わっており、その中でカウンセリング業務を行う職員のマネジメントも担当していた。職員の相談後の姿から、カウンセリングには心身共に大きな負担が掛かることが想像できたことから、カウンセリング業務とは一体どのようなものなのか、また当該職員がどのような苦労を抱えているのかを理解したいと思ったことなどが取得の背景にあると話す。
消費生活アドバイザーについては、同社でも顧客本位の業務運営の推進に役立つ資格として取得を推奨しており、同氏も入社前から取得に興味を持っていたが、消費者動向に関する幅広い知識を身に付けることは、取得当時のコンプライアンスに関わる業務だけでなく、将来にわたって役に立つと考え取得を決意したという。
多くの資格を取得したメリットは今の所属部署でも実感できるとし、「専門職の採用や委嘱業務に携わった際、これまでに得た法的知識や実務経験が役に立つことも多く、以前一緒に担当した実務担当者から感謝の言葉を掛けてもらえたときは、学びが役立ったことを素直に喜ぶことができた」と振り返る。
大長氏はこれまでのキャリアについて、福利厚生を軸に職員向けの業務に長く携わってきたとし、職員が健康で安心して気持ちよく働ける環境を整えることが会社の生産性向上につながると考える中、今担当している業務にも大きなやりがいを感じていると話す。その上で、「これからも福利厚生支援による職場環境の整備など、社内外を問わず、皆さんが笑顔で生き生きと働くための環境をつくっていく、その役割を果たしていきたい」と先を見据える。
何のための勉強か
いずれの資格試験も一度の受験で合格したという大長氏だが、そこには乗り越えるべき課題がいくつもあった。
社会保険労務士については、週に1回、土曜日に専門学校に通って授業を受け、日曜日にその復習を行い、さらに平日の通勤時間などの隙間時間を活用してテキストを読んだり、過去問を解いたりして学びを進めた。「約1年間の学びの途中、学習量の多さと学習範囲の広さに挫折しかけたこともあったが、ここで止めてしまったら自分の中でこの挑戦が負の思い出になると思い、そうならないために、結果はどうあれとにかく最後までやり切ることに注力した」と振り返る。
産業カウンセラーについては、試験が学科と実技によって行われ、毎週土曜日に行われる養成講座では実技中心に学んだという。学科対策は試験の数カ月前から取り組み、テキストを読んで過去問を解くというルーティンを毎週末続けた。「養成講座では、実際にカウンセリングを受講生同士で行い実践力を磨いたが、自身が相談する役として悩みを打ち明けたり、逆に相談を受ける役として、出会って間もない人の悩みを聞いたりすることは想像以上に難しく、学科対策より実技対策のほうが大変だった」と明かす。
消費生活アドバイザーについては、同社で取得を推奨していることもあり、同社から提供される試験対策情報や、実際に資格を取得した先輩社員のアドバイスを参考にしながら、市販の過去問を購入するなどして独学で学びを進めた。当時は大長氏自身、7歳と2歳の子どもの育児中ということもあり自宅で学ぶ時間を十分に確保できず、勉強の時間は昼休みに捻出していたという。
大長氏はリスキリングについて、何のための勉強かという目的を明確にするべきとの見解を示す。「目的を定めることで、それが仕事へのモチベーションにつながったり、ちょっとした自信を持つきっかけになったりもする。キャリアや価値観、資格などの重要度は人それぞれ異なる。だからこそ、自分にとっての学びの動機をしっかりと意識しながら取り組んでいくことが大切ではないか」と述べている。