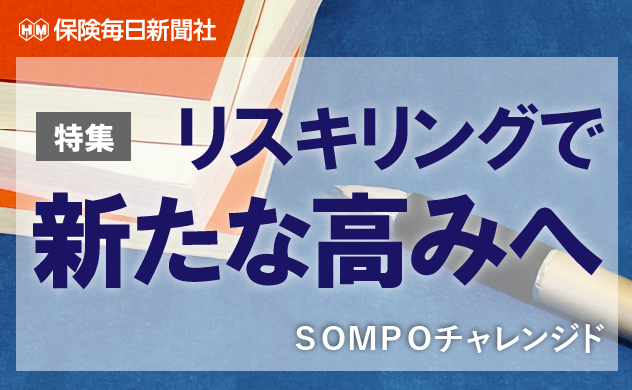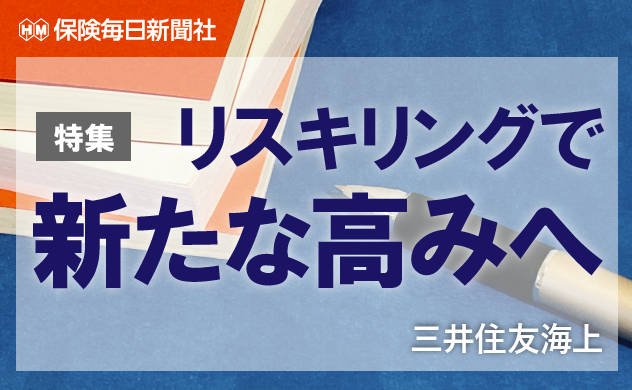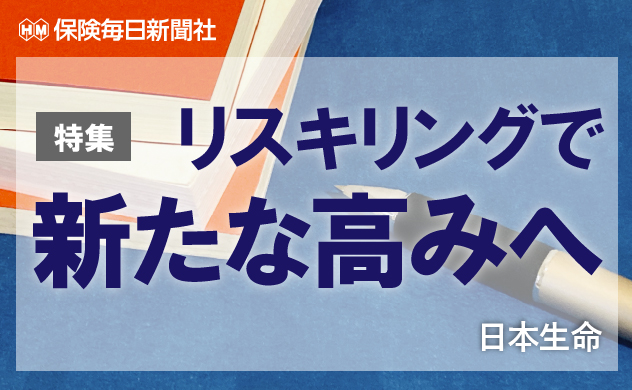コンテンツ
- ホーム
- 保険毎日新聞コンテンツ
- 特集
- 特集
リスキリングで新たな高みへ~DLI NORTH AMERICA
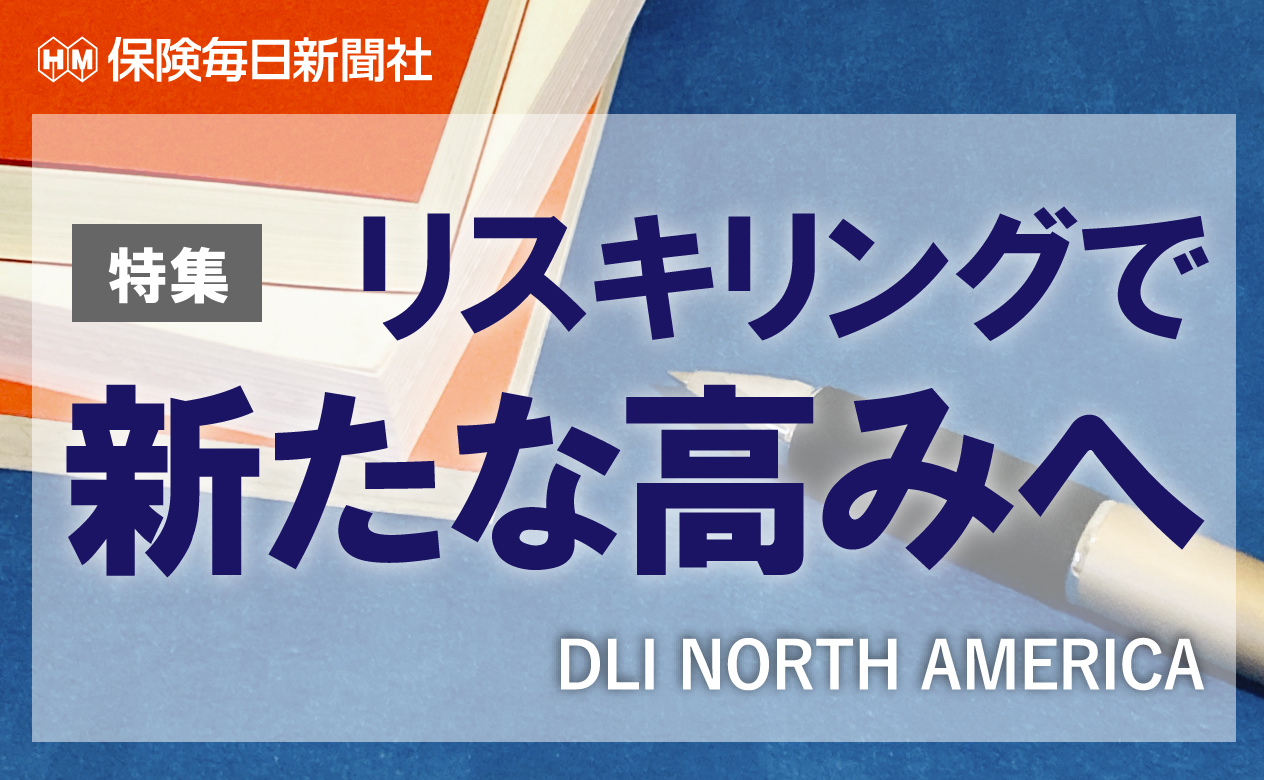
社内外でリスキリングを通じて新たな視点を獲得し、事業貢献に向けた挑戦を続ける人物を紹介する特集の今回は、第一生命グループの進藤自由平(しんどう・じゅうべい)氏。進藤氏は、国内営業、海外駐在、本社管理、外部出向と多彩なキャリアを歩みながら、現場と経営の双方の視点を養い、CMA(日本証券アナリスト)やUSCPA(米国公認会計士)の資格取得やコンサルティングファームでの勤務経験により、組織知の外に視野を広げてきた。「ときに痛みを伴うこともある」と話す一方、異なる領域の人々との接点を通じて、学び続けることに価値を見出している。
DLI NORTH AMERICA 進藤自由平 氏
知見と資格強みに海外生保事業の中核へ

Finance, Risk Management, & Accounting Research
視野を広げるために外部出向制度も活用
インド駐在で経営視点の重要性を知る
第一生命に2011年に入社した進藤氏は、名古屋の中京総合支社で営業支援業務からキャリアをスタートし、営業職員との同行や法人営業の支援を行いながら、現場の感覚への理解を深めた。その後、大阪の本社部門である関西マーケット統括部に異動し、関西の支社の統括業務を経験した。
営業支援、営業職員の採用・育成といった分野に携わる中、入社当初から志していた「海外での保険事業に携わる」という目標を実現する機会を得て、入社6年目にはインドに赴任した。日本型の営業職員チャネルの立ち上げや、現地に即した保険販売体制・オペレーションの整備に取り組み、「営業現場をつくるには、現地文化や商習慣を理解するだけでなく、より広い視点で経営全体を見ながら考えていく必要性を痛感した」と振り返る。この経験は、後のリスキリングの原動力にもなっているという。
赴任中、自ら立ち上げた営業部門が閉鎖されるという事態に直面し、「営業という狭い視点にとどまったことで、全社的な意思決定とのズレが生じたのではないかという反省があった。それからは、広い視野で経営を理解するための学びを意識的に続けるようにしている」と明かす。
帰国後は本社の海外生保事業ユニットに異動し、アジアや米国の現地保険会社の経営上の意思決定に、本社の立場から関与する業務に従事した。マーケットの中でその会社がどの位置にいるのか、業界におけるポジションの目線で相対化しないと経営判断に対する確信が持てないと感じた同氏は、開示資料や報告書に示される財務データに触れていくための一歩目としてCMAを取得した。
USCPA取得、デロイト出向での学び
19年から米国の子会社を担当し、その業績や経営行動の分析・報告に現地の会計基準を理解する必要性もあると感じた進藤氏は、USCPAの取得を決意する。仕事と育児などの家庭での時間を両立させながらの学習は簡単ではなかったが、隙間時間を活用し、短時間でも継続して学ぶスタイルを貫いた。ストップウォッチを使って細切れの学習時間を計測し、それが積み重なってまとまった時間になることを可視化するなどの工夫を重ね、累計699時間の学習で取得に必要な4科目に合格した。その要因について、「コロナ禍で通勤時間がなくなり時間に少し余裕が生まれたという、当時の状況に助けられた部分もある」と謙虚に話す。
23年には、自身の所属する会社を外から見られるような経験を積みたいという理由から、外部出向制度を利用してデロイト・トーマツ・コンサルティングに1年間出向した。金融、ファンド、製造業など、業界をまたぐ四つのプロジェクトに参画し、さまざまな知識を蓄えながらクライアントに価値を提供するという日々を過ごした。当時を「とにかく早く学ぶ力が問われ、学び方そのものを学んだ1年だった」と振り返る。ここで言う「学び方」とは、コンサルティングにおいて自身の得意領域に持ち込むのではなく、「知らないことを知りながら走る」という姿勢そのものだという。
リスキリングの先に
進藤氏は取得した資格や出向経験について、自らのキャリアアップを目的にしたものではないと語る。これまでのリスキリングを振り返り、「自分のコンフォタブルなゾーンを超えた内容を学ばねばならず、また学んだことを実際に使えるようになるにも鍛錬が必要だ。特に自分が拡げた領域に、その領域を専門として長く取り組んでいる人材がいる場合、知識や経験が劣後することでパフォーマンスも劣り、それがときに自身の精神衛生を損ねることもある。この観点から、企業が労働者にリスキリングを奨励することはかなり残酷なことだとも思っている」と打ち明ける。
続けて「ただ、こうした苦痛と引き換えに」と前置きした上で、「同じ言語で新たな領域の方々と話せるようになり、一人では見えなかったものを捉えられるようになり、それまでとは異なる風景が見えながら仕事ができたときには、やってきて良かったと感じるところだ」と述べている。