コンテンツ
- ホーム
- 保険毎日新聞コンテンツ
- 連載コラムうず
うず
貨幣文化終焉か
先日、東京豊洲にオープンしたばかりの場外市場を訪れてみた。さすがに東京の新名所。平日にもかかわらずごった返すほどの賑わいぶりだ。お目当ては豊洲の幸にあることは歴然だ。昼時ともなれば、食事の席を確保するのも容易ではない。
当日、フードコートでようやく席を取り、さて注文と、ある店舗の前の列に並んだときだ。ここは前払いで、レジの画面を自分でタッチしてオーダーするシステムになっている。そこまではいい。だが、自分の番になると、いくら探してもレジ画面に現金の項目がない。あるのは交通系カードなどの電子マネーやクレジットカードばかりだ。長蛇の列の中、現金を用意していた身としては慌てふためくばかりだった。「そんなことなら先に教えてよ」。空腹がさらに増して、腹立たしい気分になってきた。ここも人件費削減か、いやいや新紙幣への対応をやめたということか。
今年の7月3日から日本銀行では新札を発行する。新1万円札には保険業界にも関わりのあった渋沢栄一、新五千円札は教育家の津田梅子、新千円札には医学界から北里柴三郎の肖像が採用されている。気になるのは偽造防止技術だが、新札では従来の偽造防止技術に加え、肖像が見る角度によって回転する世界初の3Dホログラムが採用されている。さすが、日本が誇る紙幣だ。はて、こうした極めて高度な最新技術、一般の自販機で読み取れるのか。銀行のATMや駅の券売機などでは対応が進んでいるだろうが、全国に約400万台もある飲料水などの自販機や、駐車場の自動精算機などでは不安が残る。
世の店で現金もだめ、新札も対応できないとなれば、貨幣文化はどこへ行くのか。終焉が近づいているということか。(リュウ)



 " alt="サムネイル">
" alt="サムネイル">
 " alt="サムネイル">
" alt="サムネイル">
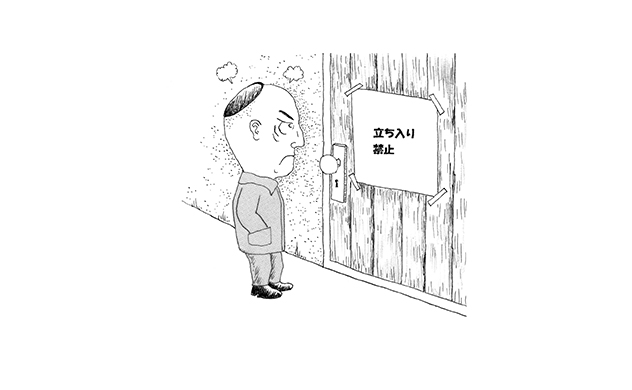 " alt="サムネイル">
" alt="サムネイル">