コンテンツ
- ホーム
- 保険毎日新聞コンテンツ
- 特集
- 特集
特集 関東大震災から100年(8)災害被災者の「こころのケア」

災害被災者の「こころのケア」
■支援者の心構えと対応のポイント 「正しい理解」と「思いやり」を
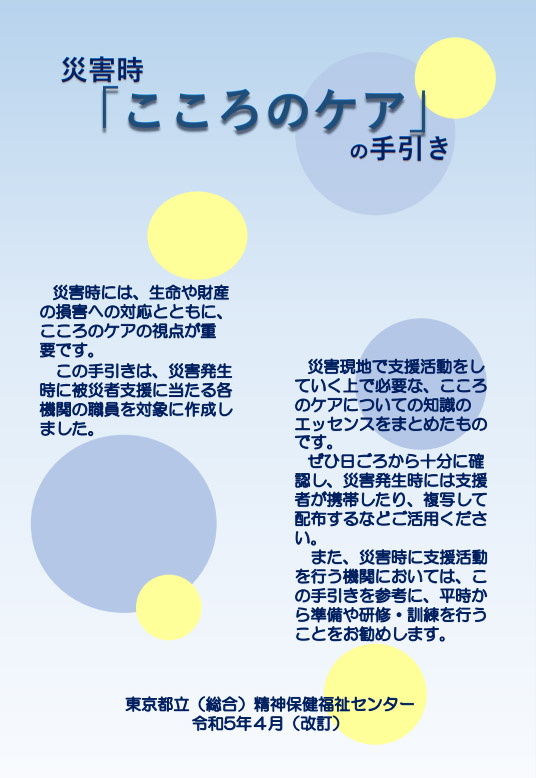
災害時の被災者支援においては、身体や財産の損害への対応と同時に「こころのケア」の視点が重要となる。東京都立(総合)精神保健福祉センターは、支援機関の職員を対象とした「災害時『こころのケア』の手引き」を発行しており、同冊子には支援者としての心構えや被災者への対応のポイントなど支援活動の際に必要となる知識がまとめられている。災害時に現地に派遣される保険会社社員にとっても、被災した顧客の心に寄り添う接し方を知る上で活用できそうだ。
被災者を支援する際は、まず体調を整え、自分の役割を正しく把握すると同時に、公的機関や交通など被災地域の正確な情報を知っておくことが基本であり、被災者の考えを尊重しながらニーズに合わせて負担をかけない範囲で支援活動を行うことが重要となる。
災害などで大きなショックを受けた際に心身に変調を来すのは人間の正常な反応であり、支援者はそれを理解し、思いやりをもって適切に対応する必要がある。
災害で生死にかかわるような体験をした人には、①苦痛な体験の記憶がよみがえってくる「再体験症状」②災害体験を思い出すことを避ける、感情が麻痺するなどの「回避・麻痺症状」③精神的緊張が高まり睡眠障害が起こる、イライラして怒りっぽくなるなどの「過覚醒症状」―の三つのストレス反応が現れやすく、症状が長引き治療が必要になることもあるが、多くの場合は時間の経過とともに徐々に回復する。
ストレス反応を軽減させる最も良い方法は傾聴であり、安易な励ましや助言をせず、相手のペースに合わせて共感する姿勢で聞くことが大切だ。怒っている人には、非難や否定をせず、やり場のない感情を受け止めた上で具体的に困っていることを聞くことが重要であり、大切な人やものを失くした人に対しては、話を聞きながら相手が悲しみの感情を自然に表出できるように促すことが大事になる。
高齢者は環境の変化により、不眠や食欲不振、せん妄などの症状が現れやすくなるが、環境を整え、人間関係を大切にして安心感を与えることが大事であり、また、隣に座る、別れ際に握手をするなど肌のぬくもりを感じさせるコミュニケーションも恐怖や怒りなどの感情を和らげる効果がある。
一方で支援者も、被災者の外傷的体験話を聞く中で精神的打撃を受け、心身に不調を来すことがあるため、睡眠障害や憂鬱(ゆううつ)、強い無気力感などストレス症状が現れた際は、組織的に対処する必要がある。
「災害時『こころのケア』の手引き」には、こういった支援者としての心構えや被災者への対応のポイントなどがより詳細に記されており、他にも、深刻な喪失体験に見舞われた人の「悲嘆反応」や、時間経過による被災者の心の動き、災害時要援護者への配慮といった知識の記載に加え、被災者向けのストレス反応チェック項目など現場で使用できる資料が添付されている。
同冊子は東京都立中部総合精神保健福祉センターのホームページから無料でダウンロードできるため、被災地で支援活動をする上でぜひ参考にしてほしい。
東京都立中部総合精神保健福祉センター

■災害派遣精神医療チーム「DPAT」 心を支えるスペシャリスト

菅原氏
災害は心に大きな負担を与えることから、災害を機に精神疾患を発症する被災者は少なくない。こうした精神保健医療の需要に対し、地域の自治体だけでは対応しきれない場合に、現地に急行して被災者の心のケアをはじめとする精神保健分野での支援活動を行っているのが「災害派遣精神医療チーム(DPAT)」だ。これまで阪神淡路大震災や東日本大震災など各地で被災者支援に携わってきた、東京DPATの精神科医師であり先遣隊総括者で東京都立中部総合精神保健福祉センターの菅原誠氏に、DPATの活動内容や災害への心構えなどを聞いた。
DPATは、大規模災害が発生した際、現地の自治体や医療機関から派遣要請を受けた場合に被災地に赴き、被災した精神科医療機関の機能補完や精神避難所などでの保健活動を行う専門の精神医療チームで、各都道府県によって組織される。
東京DPATは、都内3カ所の精神保健福祉センターと、協定を結んだ約31軒の病院の職員およそ370人で構成されており、精神科医・看護師・業務調整員が4人1チームで活動する。
DPATの活動内容はフェーズと共に変化し、発災後72時間程度までの超急性期には、機能しなくなった精神科病院からの入院患者の転院支援や物資の補給などの医療継続支援を中心に行う。
1~2週間が経ち急性期を超えると、避難所生活に馴染めず不安で不眠になる人や、せん妄を発症する高齢者、情緒不安定になる子どもなどが現れるため、避難所での精神保健相談など「こころのケア」に関する対応が始まる。
精神障がいで以前から通院していた人などは、騒々しい空間や慣れない環境の下で病状が悪化しやすく、こうした場合は地域医療機関が復旧するまでの応急対応として、DPATの医師が診察や薬の処方などを行うこともある。
発災から1~2カ月以上が経過して亜急性期および慢性期に入ると、インフラの復旧に伴い被災者も徐々に自宅に戻るため、DPATは保健師と連携し、独居の高齢者や障がい者などを戸別訪問して要支援者に受診を勧めるといった地域の保健活動を支援する。
一方で、家を失い避難所に残らざるを得ない被災者が、先行きが見えない不安から精神疾患を発症するケースが増えてくるため、こうした診療対象者を地域の医療機関につなげるのもDPATの役割になる。
同時期におけるもう一つの重要な活動が支援者支援だ。発災から2~3カ月ほど経つと、被災自治体の職員など被災者の支援に当たる人の「こころのケア」が必要になってくる。
支援者は、自身も被災者でありながら不眠不休で働き、家族を亡くすなど辛い思いを抱えていても被災者を支援し続けなければならないため、DPATが面接などを通じてアドバイスを行い、心身の健康を維持できるようサポートする。
一方で、面接の機会を設けても、犠牲者を目の当たりにしながら自分が生き延びたことに対して抱く罪悪感から面接を辞退する支援者は多く、支援者の支援は難しいのが現状だという。
近年は、被災自治体の職員が疲弊しないよう他県から応援職員を派遣する体制が徐々に整ってきているものの、完全に解決することは難しく、支援者支援は「こころのケア」の中でも重要な領域となっている。
東日本大震災を機に、厚労省はこれまで「こころのケアチーム」として活動していた災害派遣精神医療チームの活動内容の見直しを行い、2013年に「DPAT」の名称と定義を定めて全国の都道府県に設置を要請した。それを受けて、東日本大震災をはじめ多くの被災地の精神保健活動支援をけん引してきた東京都のチームも「東京DPAT」に名称を改めた。
東京DPATをはじめ全国のDPATが、災害時に起こり得るあらゆる状況を想定して日頃からさまざまな訓練を行い、被災者の心を支える災害時精神保健医療のスペシャリストとして、災害発生時に直ちに対応できるように備えている。
菅原氏は、災害への備えとして、最寄りの避難所を確認しておくこと、災害伝言ダイヤルの使い方を知っておくこと、自治体の防災アプリをダウンロードしておくことが重要だとした上で、「発災直後は生き残ることが何よりも大切だ。基本的な防災知識を身に付け、発災直後はそれに従って行動し身の安全を守る。私がかつて加入していたボーイスカウトの標語は『そなえよつねに』だが、まさにそれが重要で、事前に備えておくことが身の安全の確保と同時に、心の余裕につながる」と話す。



